gBizInfoデータ活用アイデア集
ビジネス分析から社会トレンド予測まで
1. gBizInfoとは?
gBizInfo(ジービズインフォ)は、経済産業省が提供する法人情報のデータベースです。国税庁、厚生労働省、日本年金機構など、複数の省庁が持つ企業の基本情報、財務情報、認証情報、調達情報などを集約し、APIを通じて無料で提供しています。
このデータの真価は、「公的機関の信頼できる情報」が「横断的に連携されている」点にあります。
2. 取得可能な主要データポイント
gBizInfoから取得できる情報は多岐にわたります。主なデータは以下の通りです。
- 基本情報: 法人名、法人番号、所在地、設立年月日、業種(日本標準産業分類)、従業員数
- 財務情報:(一部の上場企業・大企業)売上高、利益、総資産、純資産など
- 認証・表彰情報:
- 健康経営優良法人
- DX認定事業者
- 女性活躍推進(えるぼし、なでこ銘柄)
- 事業継続力強化計画(BCP)認定
- ISO各種認証
- 調達情報: 政府調達(物品・サービス)の実績
- 特許情報: 保有特許の概要
- 補助金情報: IT導入補助金などの採択履歴
3. 面白い使い方(活用アイデア)
単に企業を検索するだけでなく、これらのデータを組み合わせることで、多様なインサイトを得ることができます。
アイデア1:高精度な市場調査と営業リストの自動生成
目的: 潜在的な優良顧客を特定する。
手法: 複数の条件を組み合わせて、ニッチな企業リストを作成します。
- 例1:
「東京都」×「情報通信業」×「従業員数50人以上」×「DX認定事業者」 - 例2:
「大阪府」×「製造業」×「健康経営優良法人」
発展: このリストをCRMに連携し、各企業の認証情報(例:「DXに積極的なので、このSaaSを提案しよう」)に基づいたパーソナライズド営業を自動化できます。
アイデア2:サプライチェーンと地域リスクの可視化
目的: 特定の企業や業界の取引関係と潜在リスクを分析する。
手法: 「調達情報」は、どの企業がどの政府機関に何を納入したかを示します。これを分析することで、企業の取引ネットワークの一部を推測できます。
- 分析: 特定の部品(例:「半導体関連」)を調達している企業群をマッピングする。
- リスク分析: それらの企業の所在地が特定の地域(例:地震が多い地域、特定の工業地帯)に集中していないか?
発展: これにより、自社のサプライチェーン(あるいは競合のサプライチェーン)の脆弱性を評価できます。
アイデア3:社会・経済トレンドの先行指標として利用
目的: 企業動向からマクロなトレンドを掴む。
手法: 認証情報や設立年月のデータを時系列で分析します。
- トレンド分析: 「DX認定」や「健康経営優良法人」の認証を取得する企業が、どの業種・地域で、どれくらいのペースで増加しているかを可視化する。
- 仮説: 「DX認定」企業の増加率が高い業種は、今後数年で業界再編や成長が加速する可能性がある。
- 経済指標: 地域ごとの新設法人数を分析し、景気の先行指標として利用する。
アイデア4:異種データとの「マッシュアップ」
目的: gBizInfoをハブとして、他のデータと連携させ、新たな価値を創出する。
手法: gBizInfoの「法人番号」は、企業を一意に特定するIDとして機能します。
- gBizInfo + 特許データ (J-PlatPat): 企業の特許情報と財務情報を組み合わせ、R&D投資効率(売上に対する特許数など)を分析する。
- gBizInfo + 求人データ (ハローワーク等): 企業の業績や認証情報(例:えるぼし)と、実際の求人数や給与水準の関係を分析する。
- gBizInfo + 不動産データ: 特定の業種(例:ITスタートアップ)が集積する地域の変遷と、オフィス賃料の相関を分析する。
4. 結論
gBizInfoは、単なる企業名鑑ではありません。営業、マーケティング、リスク管理、経済分析、サービス開発など、あらゆる分野で活用できる「生きたデータ」の宝庫です。APIを活用し、他のデータと組み合わせることで、その可能性は無限に広がります。

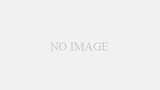
コメント